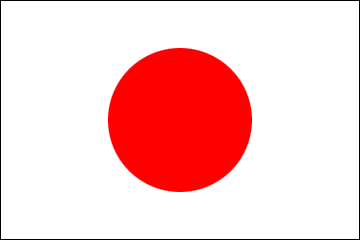山田総領事(2017.6~2020.7)の見聞禄
平成30年3月27日
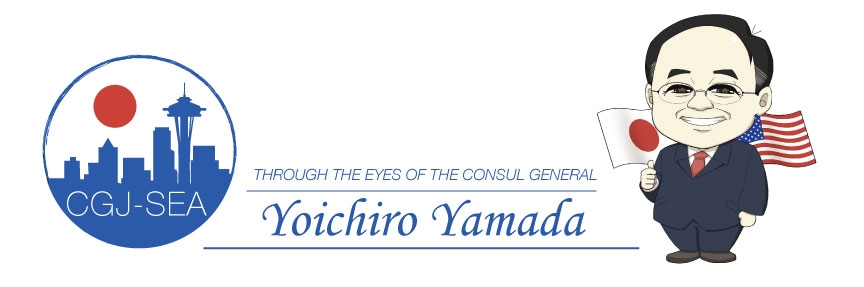
災害時にはトイレに困る

阪神・淡路大震災の後、高速道路の被害の状況
(Courtesty of Wikimedia Commons)
実は、トイレが使えなくなることなのです。停電が発生し、水道から水が流れなくなると、使い慣れた水洗トイレは流れなくなります。人間は排泄せずには生きていけません。震災後、徒歩で帰宅する最中にもトイレに行かなければなりません。なのに、職場でも、家に帰っても、街中にも、どこにもちゃんと流れるトイレがない!
日本では、今までの震災の経験から、トイレ問題の重要性についての認識が高まり、便座に取り付けるゴミ袋のような形の災害用トイレを常備する家庭が増えました。それでも、いざという時にそれが使えるかは別問題です。大震災から下水道が復旧するには1か月以上かかりますが、そのような長期間分の災害トイレがある家庭は少ないでしょう。
市町村などが応急用の簡易トイレを作りますが、それもすぐに汚れていき、汚物は溜まって溢れるばかり。物陰に隠れて用を足すことのできる男はまだ救われますが、女性は本当に大変です。用を足す回数を減らすため、水分や食料を取る量を減らしていき,心身の健康が損なわれていく悪循環ができます。ところが、トイレや排泄物といった問題は、とかく正面から議論されないまま放置されがちで、災害が発生するたびに同じことが繰り返されるのです。臭いものには蓋がされてしまうのですね。
2月23日、ワシントン大学構内で、総領事館,東北大学,ワシントン大学の協力により,防災シンポジウムが行われました。地震対策が現実の課題であるワシントン州、各地の郡や市にとって,地震対策は現実の課題です。米国側は災害担当関係者などの専門家が計80名以上出席しました。東日本大震災の際に液状化現象でインフラが大打撃を受けた浦安市の市長を務めていた松崎秀樹さんと、日本トイレ研究所代表理事の加藤篤さんが、災害時のトイレ問題の実情と得られた教訓について生々しい報告をしてくれました。アメリカ側の参加者は食い入るようにプレゼンを見ていました。
 |
 |
| 浦安市の前市長 松崎秀樹さん | 日本トイレ研究所代表理事 加藤篤さん |
5年前にケニアに在勤していたとき,超節水型トイレのプロジェクトを進めていたリクシル社の今井茂雄さんという方が,災害時に役立つトイレは電気や上下水道などのインフラの整っていない発展途上国でも役立つことを教えてくれました。現在、トイレにアクセスのない人が世界で25億人いると言われています。途上国で女性がトイレ問題で大きな悩みに直面していることも災害時の日本と同じです。特に少女はトイレを使いたくないあまり学校に行くことを嫌がり、就学率の低下の重要な要因になっています。
ケニアには多くのドナー国や国際機関が支援活動をしていましたが,トイレ問題で持続可能な解決方法を提示し、実際に協力していたのは日本の団体でした。日本にはウォシュレットのような快適なトイレ技術もあります。トイレという,他の国の人があまり注目しない大事な分野で,災害対策や途上国援助などの面でこれからもリードしていって欲しいと思います。