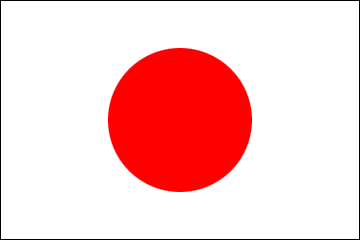山田総領事(2017.6~2020.7)の見聞禄
平成30年12月21日
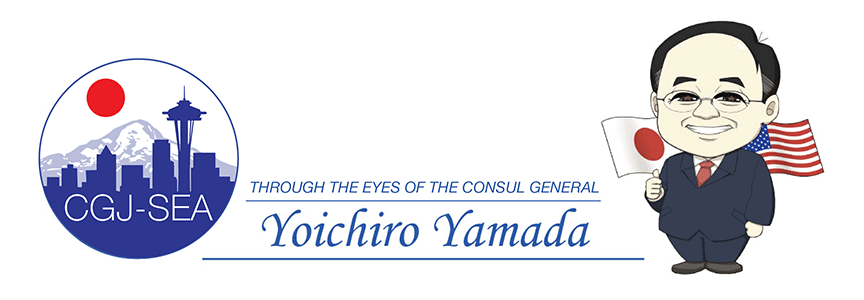
東京、シアトル経由でポーランドに帰ったシベリアのポーランド孤児の話

(左から) テレサ・インディク・デイヴィス名誉領事、マーサ・ゴルンビックさん、
パウェル・クルンパさん(ポーランド・ホーム・アソシエーション代表)、
私、アンナ・ドマラツカさん(シベリア孤児の娘)
11月10日、私は二世ベテランホールでベテランズ・デイの記念行事に出席した後、ポーランド文化会館で行われた記念式典に出席しました。100年前のこの日(時差を考えるとヨーロッパではもう11月11日でしたが)、第一次世界大戦が終了し、同日、ポーランドが123年ぶりに独立を回復したのです。私がポーランド人の式典に招待されたのは、約100年前にシアトルで起こったポーランド人にまつわる出来事に日本が深くかかわっていたからです。
ポーランド人は1795年に国土をプロシアとロシアに分割・併合されましたが、その後も独立の回復を目指して何度も蜂起しました。そのため、ポーランドに対するロシアの弾圧は厳しく、多くの政治犯や鉄道建設に徴用された労働者などがシベリアに送られ、過酷な条件の中で強制労働をさせられました。その子孫もあわせ、当時のウラジオストクやシベリア極東には約4~5万人のポーランド人が暮らしていたといいます。

シベリア孤児と日本人看護婦(福田会、1922年)
※日本ポーランド関係史(彩流社刊)P90より引用
1917年にロシア革命が発生すると、赤軍と白軍の間で内戦が勃発します。混乱の中で、ロシア各地に住んでいたポーランド人達も難民となって極東に流れ込み、その数は15万~20万人に達したと言われています。混乱の中で、多くのポーランド人が命を落とし、多くの孤児が発生しました。第一次世界大戦の終了とともにポーランドは独立を回復したので、ウラジオストクでは、孤児たちをポーランドに送り届けようとポーランド救済委員会が発足します。しかし、ロシア経由のルートは内戦のため危険で通ることができません。委員長のアンナ・ビエルキエヴィチ女史は最初、ほかの国々に救済を訴えましたがうまくいかず、最後に東京に乗り込み、外務省に窮状を訴えました。外務省から連絡を受けた日本赤十字社が中心となり、仏教団体なども支援して、大規模な難民救済活動であるポーランド孤児の保護が行われたのです。

ポーランド・ホーム・アソシエーションの写真
1920年と22年の2回にわたり、陸軍の船で計765人の孤児がウラジオストクから敦賀港に着きました。第一陣の375名の孤児たちは、東京の施設に送られました。そこですっかり元気を回復した孤児たちは、8回に分けて日本の船で横浜からシアトルに渡り、米国を横断してポーランドに帰りました。第二陣の孤児たち390人は大阪に滞在し、スエズ運河経由の航路を取りました。このようにして765人の孤児が無事にポーランドに戻ることができたのです。シアトルのポーランド文化会館には、ポーランドへの帰途、シアトルに到着した孤児たちの大きな記念写真が掲げられており、日本語、ポーランド語、英語の三か国語で説明があります。

イエジ・ストシャウコフスキ氏
(写真提供:イジドルクザックさん、ウィキメディア・コモンズ)
これらの孤児たちは、青年になっても相互の連絡を絶やさず、「極東青年会」という互助組織を立ち上げました。1938年当時の記録では、会員数は434名だったそうです。会の発起人であったイエジ・ストシャウコフスキ氏は、第二次世界大戦が始まりポーランドが再びドイツとソ連に分割されると、ドイツ軍に占領されたワルシャワで発生した孤児たちのために孤児院を立ち上げました。同時に、「特別蜂起部隊イエジキ」を組織して、孤児院の子供たちもあわせてポーランド全体で数千人がこの地下組織に加わりドイツ軍に抵抗したということです。ちなみに、彼は共産主義体制下のポーランドを生き抜き、自由な社会になった1991年に亡くなります。ほかにも、シベリア孤児の中には、レジスタンス運動で逮捕されてアウシュビッツに収容され、そこから生還した人もいます。シベリア孤児の多くは、何という波乱に富んだ人生を生きたのでしょう!

11月10月の記念行事でのスピーチ
独立100周年記念行事では、ポーランド名誉領事のテレサ・インディク・デイヴィスさんが孤児のエピソードに触れた挨拶をしました。私も挨拶するよう求められ、ポーランドに勤務していた(1999年~2001年)ことを含めて自己紹介し、ポーランド孤児を巡る昔のエピソードや、1996年に神戸の震災孤児たちをポーランドが温かく受け入れてくれ、年老いたシベリア孤児の方々が子供の時の経験を話してくれたことなどを紹介しました。スピーチが終わると、私がスピーチの中で触れたポーランドで歌われる誕生日の歌「Sto Lat(100歳の意味)」を誰ともなく歌いだし、約200人のお客さんたちの大合唱になりました。会場にはシベリア孤児を父に持つアンナ・ドマラツカさんも来ており、お目に掛かることができました。彼女は既に日本で孤児ゆかりの土地を訪問したことがあるそうで、来年には父親の足跡を訪ねて、ハルビン、ウラジオストク、敦賀、東京というルートで旅行する計画を立てているそうです。

「Sto Lat」の合唱
11月15日には、ベナロヤ・ホールでポーランド人のピアニスト、ヤヌシュ・オレイニチャクさんによる、ポーランド独立100周年記念のショパンのコンサートが行われ、家内と息子の3人で聴きに行きました。オレイニチャクさんは、11月に入ってから日本の複数の都市でコンサートを行い(私もですが、日本人は本当にショパンが好きですよね!)、14日の晩はニューヨークのカーネギーホールで弾いていたということです。オレイニチャクさんは、映画「戦場のピアニスト」でピアノの演奏を担当したピアニストで、この映画は私と家内の出会いのきっかけになった映画ですので、特別の思いがあります。オレイニチャクさんは、演奏プログラムを変更し、ポーランド魂を表現する曲のオンパレードとなりました。ユダヤ人のピアニスト、ヴワジスワフ・シュピルマンさんがドイツ軍に占領されていたワルシャワの隠れ家の廃墟でドイツ人将校に見つかったとき、自身がピアニストであることを証明するために弾いたノクターンNo.20遺作から始まり、第一部の最後には軍隊ポロネーズ、第2部の最後には英雄ポロネーズです。そして、アンコールの最後は革命エチュードで締めました。私にとっては、久しぶりに音楽で感動する幸せなひと時でした。

ヤヌシュ・オレイニチャクさん
(写真提供:アダム・ビエラフスキさん、ウィキメディア・コモンズ)