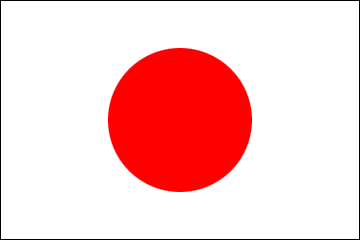山田総領事(2017.6~2020.7)の見聞禄
令和元年5月23日
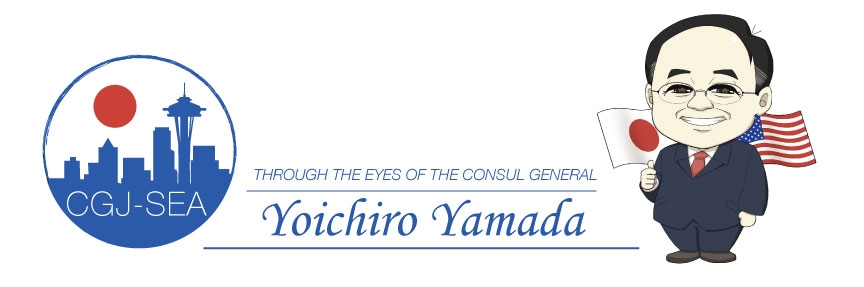
不当離婚の問題に取り組んでいます。その2
前回、米国人男性と結婚した日本人女性の家庭内暴力被害や、不当な条件での離婚に追い込まれている現実について書きました。
国際離婚問題は個人のプライバシーにかかわるデリケートな事柄で、被害者の女性もオープンに話すことはありません。ゆえに,井上弁護士から話を聞くまでは,不当離婚に伴う大きな社会問題があることを知りませんでした。話を聞いた後も,何かやるべきと感じつつ何ができるのかわかりません。
私がシアトルで働き始めて5か月たった2017年11月のこと、日系人リーダーの一人で、社会的に脆弱な立場にあるアジア系住民に各種サービスを提供するAsian Counselling and Referral Service (ACRS)というNPOの事務局長を長年務めてきたダイアン・ナラサキ事務局長を訪問しました。彼女にこの話をしたところ,彼女は長年の同僚で著名な人権活動家であるトニー・リーさんを紹介してくれました。12月初めにリーさんを訪問すると、州上院法務委員長のジェイミー・ピーダーセン上院議員を,同上院議員は州の法的支援局(OCLA)のジェイムズ・バンバーガー局長をそれぞれ紹介してくれるという具合に繋がっていき、議会の予算手続きや州議会のスケジュールなどについて多くの知識を得ることが出来ました。しかし,州議会は1月初めから始まるので,余り時間がありません。とりあえず2018年は移民の離婚問題への取り組みに対する補正予算の提案として活動を始めました。
早速,資料を作り,井上弁護士と一緒に,州議会の関連委員会の議員に対する説明を開始しました。議場にはいつも多くのロビイストたちが廊下に控えていて、議員が議場から現れると短時間で熱っぽく陳情しています。会期中の議員は極めて多忙ですが,州議員の方々は、忙しい審議の合間を縫って私たちのために時間を作ってくれました。当時、上院下院とも民主共和両党の議席が一票差で拮抗する中で,両党があらゆる問題で厳しい折衝を行っていました。私たちが持ち込む移民の配偶者・離婚問題も、党派間の対立の種になってしまうのでしょうか?
しかし,幸いなことにこれは杞憂でした。議員の中には、我々の話を聞いて、このような不正がワシントン州で許されるべきでないと真っ赤に怒って協力を約束してくれる人もいました。議員たちは次に会うべき議員についてアドバイスをくれ、我々は次々にアポを申し込み、3月の会期終了までには会談した議員の数は30名を超え、皆快く支援を約束してくれました。
そして、補正予算において、NPOのIFJC (International Families Justice Coalition)を支援する予算措置が認められたのです。これは州議会がこの問題を認知するとともに、困窮した被害者に対する法的支援と法曹実務者に対する啓蒙というIFJCの活動内容を,公的に支援する価値ある活動と認めたことを意味します。ワシントン州の議員が我々の話に耳を傾けるだけでなく、自らイニシアチブをとって予算をつけるという形で政策化するという能動的な関与の姿勢を見て、アメリカの民主主義の良さに触れたことを感じました。その後も話合いを続けた結果,2019年5月現在,この問題について話をすることのできた議員の数は、上下両院で50名近くに上ります。
議員の皆さんと話しているうち,私には徐々に総領事館の果たすべき役割が見えてきました。この問題に関する社会啓蒙と,予防のための働きかけの2つです。
外国出身の女性に対する家庭内暴力の問題は社会に蔓延していて,意外に身近にある問題にも拘らず,そこそこ円満な生活をしている人にはどうもピンとこないのです。実際,戦後に「戦争花嫁」として米国に渡った日本人女性や,90年代にはフィリピンやロシア出身で「郵便注文花嫁」として米国に来た女性たちの中にも,夫に捨てられたり暴力を振るわれたりした被害者が多数いました。しかも人口が増加し続けるシアトルでは、この問題はより一層深刻さを増している状況にあり、社会の人にこの問題を知ってもらう必要があります。多くの人が知るようになれば,身近にある不審なことに気がついて,助け合うことが出来るようになります。そこで,昨年4月,シアトル・タイムズの社説意見欄に寄稿しました。
また、ライトハウスの2018年9月号が、離婚について特集を組んでくれました。
日本人社会や日系米国人社会での集まりでは,この問題について折に触れて言及しています。また、名誉領事も含めて40カ国以上の代表が在籍しているシアトル領事団でもこの問題を紹介しました。捨てられた女性を実際に助けたという名誉領事もいる一方,この問題について全く知らなかったという人もいました。昨年9月、全米の日米協会の代表者がシアトルに集まった際にこの問題に言及したところ,あとで多くの方から自分の州でも同じ問題があるという反応をいただきました。
世界で一番大きなロータリークラブの一つであるシアトル・ロータリークラブでも、ぜひこの問題を提起したいと考えました。幹部に相談したところアイデアが採用され,国際婦人の日の2日前の3月6日の定例ランチで議論をしようということになり、関連する問題に取り組むNPO(Northwest Immigrant Rights Project, API Chaya, IFJC)に声をかけた結果、ラテンアメリカ,アジア,東欧出身の女性の直面する問題について,プレゼンとパネルディスカッションが行われました。
また、シアトルのテレビ局KING5でアンカーを務めるローリ・マツカワさんは、井上弁護士や私に取材したことを特集として、ニュース内で放送してくれました。これを見たというアメリカ人の複数の友人から、温かい言葉をいただいています。
配偶者問題の予防のために何ができるでしょうか?問題の実態に照らして考えると、妻と夫がそれぞれの法的な権利や義務を認識することと,不当な離婚合意書の作成・受理を防ぐことが重要です。そこでまずは,国際結婚している従業員の多い組織,例えばシアトルの大企業や陸軍・海軍基地の幹部と話をすることが有意義だと考えました。陸軍基地,海軍基地の司令官にこの件を話したところ,司令官たちは,“揺るぎない日米同盟関係と米軍の高い士気のためには,国際結婚をした軍人が健全な家族関係を持つことが重要である”として,私の問題提起を正面から受け止めてくれました。部隊の法律顧問らと話合って知恵を出し合い,今後は,基地の中での講習会や,国際結婚した新婚者たちのために,法的な権利義務を書いたパンフレットを作成することなどを、米軍と協力して実現したいと考えています。
また,州の複数の議員から,離婚合意書の確定の前に外国人の妻がその内容を理解していることを確認する措置の導入や法制化,離婚合意書作成の前に中立的な弁護士による早期の調停を法的に義務づけること、もし外国人伴侶が離婚合意書の内容を理解せずに署名をしてしまった場合は届書の撤回ができることを合法化するなどのアイデアも寄せられました。更に、裁判所で係争案件となった場合には,判事が問題の社会的な背景を理解しているかどうかで判決が左右されます。ところが、判事の間でもこの問題への理解は不十分のようなのです。IFJCは州裁判所に働きかけることで、配偶者問題に関する判事の研修プログラムを実施しようとしています。
今まで日米政府間では,離婚の際に母親が子供を日本に連れ去るハーグ条約関連の問題が強調されてきました。一方,不当な離婚の非情な結末については,個人の問題として,顧みられることはなかったように思います。国際結婚が増加するのに伴って、離婚の数もまた増え続けることでしょう。これらの情勢を踏まえ、総領事館の業務としては単に証明書の発行に留まらず,アメリカと協力して何が出来るか,社会の必要性の観点から更に検討していく必要があると考えます。
日本人同士の結婚であっても色々ありますが、アメリカ人との結婚も美しいラブストーリーとなるとは限りません。時には不幸な結果を伴う“賭け”になる場合があることも、理解していただきたいと思います。国際結婚は,家族や友人の助けからも遠く離れた外国で,言葉も生活習慣も価値・規範も異なるパートナーと運命をともにするという重大な選択です。一時的な熱情や打算によって結婚するのでなく,相手が一生の間,必要な信頼を寄せ続けられる人物かを冷静に考え,さらに日本人同士の結婚とは異なる国際結婚上での問題に関する知識(自分の権利と義務)を身につけたうえで決めること。そして,ひとたび結婚して米国に来たら,いざ困ったときに相談できるようにコミュニティや社会と繋がりを持つこと,これこそが不当な離婚に苦しまないための最大の予防策だと思います。