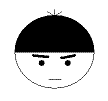イベント情報
歌舞伎Q&A
歌舞伎初心者くっちーの基本的な質問に、シアトル在住歌舞伎愛好家、シアトル大学村山元英先生、桜祭実行委員会の佐々木豊氏が答えてくれました。
*みどころ等両氏のご意見は、個人のご意見であり、外務省及び国際交流基金の見解もしくは文化解釈をあらわすものではありません。
*このコーナーは歌舞伎の基本についてご理解を深めていただけるよう作成したものです。より詳細な情報等については、書籍等でご確認ください。
紀伊國屋書店 笹川店長お勧めの歌舞伎に関する本はこちらをクリック
‘シアトル大学 村山元英先生’のご紹介
昭和9年東京生まれ。シアトル大学教授。千葉大学名誉教授。商学博士。最終学歴は米国シートンホール大学・大学院修了。専門研究は、「国際経営学」「経営人類学」「経営戦略論」を中心に、広義の経営学/経営管理論/経営環境論/都市・地域研究/比較文化論など。
長唄が趣味で、十一代目市川海老蔵の襲名披露公演でも河東節を歌われた。昨年歌舞伎をテーマとしたシンポジウムをシアトル大学で開催。 (詳細プロフィール)
‘桜祭実行委員会 佐々木豊’氏のご紹介
シアトル桜祭・日本文化祭実行委員会委員。今流なら「歌舞伎オタク」。 芝で生まれて深川育ち、「ひ」と「し」の発音の区別がつかない生粋の下町っ子。芸人と職人の中で江戸の名残りを肌で感じて育った最後の世代。 祖父は月岡芳年などを擁した明治期の浮世絵版元。 滞米40年、ボーイング社勤務を経てグラフィックデザイナーとして独立、一生現役。 本業のかたわら日本舞踊と長唄三味線の教授である夫人と共にボランテアとして30年にわたりシアトル桜祭・日本文化祭を支えてきている。
‘くっちー’の紹介
シアトル在住の36歳。歌舞伎についての知識はほとんどない。本人が自信をもって曰く「中村獅童と松本幸四郎はCMで見たことがある。」 山形県酒田市で黒森歌舞伎を一回、東銀座歌舞伎座で一幕だけ歌舞伎を見たことがある。
Q1; 歌舞伎ってなんですか?
![]() 歌舞伎は、能・狂言・文楽と並んで、日本の四大伝統演劇のうちの一つです。歌舞伎は250 年以上続いた江戸時代(1600~1868年)の平和の中で生まれ育ちました。当時台頭した町人文化の好みが、歌舞伎の絢爛たる衣装や舞台、演目に反映されており、演目には伝説のヒーローもいれば、義理と人情の折り合いをつけようとする庶民も出てきます。他の伝統演劇とは対照的に、歌舞伎は現在も大変人気があり、東京の歌舞伎座、京都の南座、大阪の松竹座などの劇場で、熱心な観客に向けて定期的に公演されています。
歌舞伎は、能・狂言・文楽と並んで、日本の四大伝統演劇のうちの一つです。歌舞伎は250 年以上続いた江戸時代(1600~1868年)の平和の中で生まれ育ちました。当時台頭した町人文化の好みが、歌舞伎の絢爛たる衣装や舞台、演目に反映されており、演目には伝説のヒーローもいれば、義理と人情の折り合いをつけようとする庶民も出てきます。他の伝統演劇とは対照的に、歌舞伎は現在も大変人気があり、東京の歌舞伎座、京都の南座、大阪の松竹座などの劇場で、熱心な観客に向けて定期的に公演されています。
Q2; 歌舞伎は男だけで演じるそうですが、なぜ男だけなのですか?
![]() 歌舞伎初期の演者は基本的には女性でした。歌舞伎は1603年、出雲大社の巫女だった阿国が、京都で最初に演じた舞踊と軽演劇に端を発すると考えられています。しかし、女歌舞伎一座の演者は、遊女として売春も行っていたため、徳川幕府はこれを許さず、1629年に禁令を出して女性が舞台に立つことを違法としました。その後、若衆歌舞伎が人気を博しましたが、1652年にはこれも禁じられました。若い役者が売春行為を行って、公衆道徳の上で逆効果だったからです。
歌舞伎初期の演者は基本的には女性でした。歌舞伎は1603年、出雲大社の巫女だった阿国が、京都で最初に演じた舞踊と軽演劇に端を発すると考えられています。しかし、女歌舞伎一座の演者は、遊女として売春も行っていたため、徳川幕府はこれを許さず、1629年に禁令を出して女性が舞台に立つことを違法としました。その後、若衆歌舞伎が人気を博しましたが、1652年にはこれも禁じられました。若い役者が売春行為を行って、公衆道徳の上で逆効果だったからです。
女性も少年も舞台に立つことを禁じられたため、歌舞伎は成人男性役者の演劇となり野郎歌舞伎とよびます。ただし、野郎歌舞伎の上演続行が許可されるに当たって、幕府は役者がみだらな表現を避け、狂言のようなもっと現実的な決まり事(芝居)を演ずるよう求めました。
近代において歌舞伎に女優を取り入れようという試みもありましたが、失敗に終わりました。女形は歌舞伎の伝統と不可分の存在なので、女優をもって代えようというのは全く思いもよらないことなのです。
Q3; 「歌舞伎」の意味、語源を教えてください。
![]() 「かぶく(傾く)」は「かたむく」の旧語で頭を傾げるような異常な行動をさし衝撃的、異端的、流行の、といったニュアンスがあり、そのような人達を「かぶき者」とよび、人気のあった阿国の一座やその模倣者たちの演技を「かぶき踊り」とよびました。
「かぶく(傾く)」は「かたむく」の旧語で頭を傾げるような異常な行動をさし衝撃的、異端的、流行の、といったニュアンスがあり、そのような人達を「かぶき者」とよび、人気のあった阿国の一座やその模倣者たちの演技を「かぶき踊り」とよびました。
後に歌い、踊る女という当て字で「歌舞妓」となり「妓」を芸、芝居という意味合いの「伎」に代え「歌舞伎」となったのは近世の事です。
Q4; 地方(じかた)とはなんですか?
![]() 地方は歌舞伎の音楽を担当する人々です。歌舞伎の音楽で最も重要な楽器は、何といっても三味線です。観客を前にした舞台で奏でられる音楽としては、抒情的な長唄があり、浄瑠璃(じょうるり)、常磐津(ときわず)、清元(きよもと)もあります。標準的な長唄の演奏は、複数の唄方、三味線奏者に太鼓,鼓と笛の奏者で行われます。三味線以外の楽器を総称して「鳴り物」とよびます。
地方は歌舞伎の音楽を担当する人々です。歌舞伎の音楽で最も重要な楽器は、何といっても三味線です。観客を前にした舞台で奏でられる音楽としては、抒情的な長唄があり、浄瑠璃(じょうるり)、常磐津(ときわず)、清元(きよもと)もあります。標準的な長唄の演奏は、複数の唄方、三味線奏者に太鼓,鼓と笛の奏者で行われます。三味線以外の楽器を総称して「鳴り物」とよびます。
舞台上の音楽のほか、舞台の袖でも唄方や三味線・笛、および様々な打楽器の奏者が種々のBGM や音響効果を出すのです。
また、歌舞伎に見られる特殊な効果音としては、拍子木を互いに打ち合わせたり、木の板を叩いたりして劇的な鋭い音を出すものがあります。
今回は長唄唄方、三味線各々2名に鳴り物の地方さんがいらっしゃいます。ご期待ください。
Q5; 花道とは何ですか?
![]() 歌舞伎の舞台につながる客席をとおる通路のことを花道といい、演目に応じて通路に使われたり、廊下として使われたりします。花道は場面に応じて様々に利用される舞台であるだけでなく、役者と観客が一体になる機会を演出します。歌舞伎に欠かすことのできない要素です。
歌舞伎の舞台につながる客席をとおる通路のことを花道といい、演目に応じて通路に使われたり、廊下として使われたりします。花道は場面に応じて様々に利用される舞台であるだけでなく、役者と観客が一体になる機会を演出します。歌舞伎に欠かすことのできない要素です。
結婚式の二次会で花道をつくる、花道を飾る、最後の花道などにあるように、花道は注目を集める場所です。
ベナロヤホール・リサイタルホールには残念ながら花道はなく、今回のパフォーマンスでは花道を使いません。
Q6; 歌舞伎役者が「みえ」をきるといいますが、「みえ」って何ですか?
![]() 見栄っ張りや大見得をきるなどの言葉がありますが、歌舞伎用語の「みえ」からきています。「みえ」は演技途中でポーズをつくって一瞬ストップモーションのように静止する演技で、注目を集め、観客に印象づける効果があります。
見栄っ張りや大見得をきるなどの言葉がありますが、歌舞伎用語の「みえ」からきています。「みえ」は演技途中でポーズをつくって一瞬ストップモーションのように静止する演技で、注目を集め、観客に印象づける効果があります。
大きな見得「大見得」は今回のパフォーマンスでは石橋の中で見ることができますが、小さな見得は随所にみられます。
「大見得」の際、眼がおおきく見開かれ、目が片方による動きがありますが、その動きは普通ではない表情で観客に注目させる為で、正確には片方の眼だけを寄らせます。
Q7; 「みえ」や「千秋楽」以外に、歌舞伎から発生した言葉はありますか?
![]() はねる: 歌舞伎でその日の公演を終えることをさします。
はねる: 歌舞伎でその日の公演を終えることをさします。
大根役者: 上手ではない役者のこと。大根はお腹にあたらない(ヒットしない)ことから、役者の叱咤激励をかねてかけ声をかけていたのが始まり。
おはこ(十八番): もっとも得意とするもの。市川家の得意芸を十八選び、大事に守ってきたことが始まり。
その他かぶりつき(舞台際の席)、とちり席(見やすい席)などの言葉も歌舞伎からでたと考えられています。
Q8; 歌舞伎役者は派手なメイクをしていますが、なぜ白く塗ったり、顔に線を引いたりするんですか?
![]() 歌舞伎で白く顔を塗るのは「白塗り」といいます。蝋燭などの照明しか無かった時代は舞台も薄暗くその中で目立つ化粧が考えられました。白塗りの上の極端な化粧は、歌舞伎の有名なトレードマークの一つで「隈取り(くまどり)」といいます。時代物で使われるこの仮面のようなスタイルは約100種類あり、用いる色やデザインが役柄の特徴的な側面を象徴しています。赤は「善」を表わすことが多く、美徳や情熱、超人的な力の表現に用いられ、一方青は「悪」で、嫉妬や恐怖など否定的な特色を示します。
歌舞伎で白く顔を塗るのは「白塗り」といいます。蝋燭などの照明しか無かった時代は舞台も薄暗くその中で目立つ化粧が考えられました。白塗りの上の極端な化粧は、歌舞伎の有名なトレードマークの一つで「隈取り(くまどり)」といいます。時代物で使われるこの仮面のようなスタイルは約100種類あり、用いる色やデザインが役柄の特徴的な側面を象徴しています。赤は「善」を表わすことが多く、美徳や情熱、超人的な力の表現に用いられ、一方青は「悪」で、嫉妬や恐怖など否定的な特色を示します。
Q9; 歌舞伎は元々庶民文化とのことですが、どのように日本文化として確立したのでしょう?
![]() 初期の歌舞伎は女性が演じており、徳川幕府がこれを禁じたことはQ2で述べました。
初期の歌舞伎は女性が演じており、徳川幕府がこれを禁じたことはQ2で述べました。
法的に男性役者の出演が認められてから、歌舞伎は大きく進歩しました。
初代市川団十郎(1660~1704年)が江戸で力強い男性的な荒事の演技様式を切り開く一方、初代坂田藤十郎(1647~1709年)は上方(現在の京都・大阪地域)で繊細かつ写実的な和事の様式を発展させました。
歌舞伎の舞台は能の舞台から徐々に発展していったものですが、引幕が加わり、より複雑な何幕もある芝居の上演に一役買いました。観客の中を通る花道が広く用いられるようになり、現在標準となっている歌舞伎の華やかな入退場の場となりました。また、回り舞台が最初に使われたのは1758年です。
18世紀の町人文化の中で、歌舞伎は人形芝居である文楽と競ったり協調したりする関係を育てていきました。近松門左衛門(1653~ 1724年)は、1703年以降は文楽の脚本に専念しましたが、歌舞伎のための脚本もいくつか書いており、日本最高の劇作家の一人と目されています。この頃の一時期、歌舞伎は上方では人気面で文楽の陰に隠れていました。挽回を期すための努力によって、多くの文楽芝居が歌舞伎に取り入れられ、役者は人形の特徴的な動きさえ真似るようになっていきます。
歌舞伎は町人文化の一部となっていましたが、1868年の徳川幕府の崩壊で、その町人文化の基礎だった社会構造全体も、武士階級も消え去りました。成功こそしなかったものの、西欧の衣装や理念を歌舞伎に取り入れようという試みもありました。また、伝統的な歌舞伎の演目に回帰しようと強く主張する人もいました。20 世紀になると、岡本綺堂(1872 ~ 1939 年)や三島由紀夫(1925~ 70 年)などの作家が、直接歌舞伎の世界とはかかわりがなかったにもかかわらず、新歌舞伎運動の一環としていくつか脚本を書きます。これらの脚本は、伝統的形式と近代演劇からの新機軸を組み合わせたものでした。
その一部は、伝統的な歌舞伎の演目に取り入れられています。
歌舞伎は、芝居の上演においても、互いに密なつながりを保ちながら歌舞伎界を形作る役者一門のあり方においても、その伝統的ルーツに忠実な一方で、今日では日本の娯楽産業においても欠くことのできない力強い存在となっています。歌舞伎の花形役者は日本で非常によく知られたスターで、テレビや映画、演劇の伝統的・現代的役柄に頻繁に登場します。たとえば、有名な女形、五代目坂東玉三郎(1950 年~)は歌舞伎以外の多数の演劇や映画でも演じており、ほとんどいつも女性役ですが、何本かの映画監督もしています。最近では中村獅童が日本のみならず海外の映画にも出演し、CMにも登場しています。(Web Japanより抜粋、一部加筆)
Q10; 歌舞伎の演目について教えてください。
![]() 大歌舞伎の演目は、時代物・世話物・所作事という三つの分野に大きく分けられます。
大歌舞伎の演目は、時代物・世話物・所作事という三つの分野に大きく分けられます。
今日演じられている演目の約半数は、もともと文楽のために書かれたものです。
時代物は、武士階級がかかわる同時代の出来事をしばしば取り上げますが、徳川幕府の検閲官との摩擦を避けるため、多少なりとも改変され、舞台も江戸以前の時代に移されました。その一例が有名な演目である『仮名手本忠臣蔵』で、1701 ~ 03 年の赤穂浪士47 人の起こした仇討ち事件の物語ですが、その舞台は室町時代(1333 ~ 1568 年)初期に設定されています。
世話物は、台詞も衣装も時代物より写実的でした。しばしば、起こったばかりのスキャンダルや殺人事件、心中事件を取り上げたので、新しく書き下ろされた世話物は、観客にとってほとんどニュースの報道のように受け止められたかもしれません。後に登場した世話物の変型が生世話物(より生々しい世情劇)で、19 世紀初めに人気を博しました。これらの芝居は社会の底辺層の現実的な描写で知られましたが、やがて扇情的傾向を増し、手の込んだ舞台仕掛けで暴力的・衝撃的なテーマを扱うことによって、飽きっぽい観客の歓心を買おうとしました。『京鹿子娘道成寺』などの舞踊作品は、しばしばトップの女形の才能の見せ場として演じられています。(Web Japanより抜粋、一部加筆)
Q11; 無形世界遺産とは何ですか?
![]() 無形遺産条約は、これまで民族文化財、フォークロア、口承伝統などと呼ばれてきた無形の文化を人類共通の遺産としてとらえ、保護していくことを目的に作成され、2003年の第32回ユネスコ総会において、賛成120カ国、反対0、棄権8カ国で採択されました。日本は2004年6月、3番目の締約国として条約を締約しています。日本の伝統文化としては、歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽が一覧表に記載されています。
無形遺産条約は、これまで民族文化財、フォークロア、口承伝統などと呼ばれてきた無形の文化を人類共通の遺産としてとらえ、保護していくことを目的に作成され、2003年の第32回ユネスコ総会において、賛成120カ国、反対0、棄権8カ国で採択されました。日本は2004年6月、3番目の締約国として条約を締約しています。日本の伝統文化としては、歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽が一覧表に記載されています。
Q12 鷺娘、石橋の見どころを教えてください。
![]() 白い綿帽子姿の花嫁を白鷺に見立てての幕開きの美しさから、鳥の動きを真似た振りをまじえて恋に苦しむ女心を描いています。「引き抜き(衣装の早変わり技法)」で町娘に変わり、最後は鷺の精に戻り狂いながら終わります。何度かの早変わりを手伝う「後見」さんとの息のあった早変わりが、鷺娘の見どころです。
白い綿帽子姿の花嫁を白鷺に見立てての幕開きの美しさから、鳥の動きを真似た振りをまじえて恋に苦しむ女心を描いています。「引き抜き(衣装の早変わり技法)」で町娘に変わり、最後は鷺の精に戻り狂いながら終わります。何度かの早変わりを手伝う「後見」さんとの息のあった早変わりが、鷺娘の見どころです。
石橋の見どころは、長いたてがみを振る男獅子。立ち役のダイナミックな動きと、女形による雌獅子の動きの対比でしょうか。
Q13 今回の事業はシアトルでの初歌舞伎ですか?
![]() 50年代に吾妻徳穂師の率いた吾妻歌舞伎が来市しています。これには子息の現人間国宝中村富十郎さんも参加しておられたようです。
50年代に吾妻徳穂師の率いた吾妻歌舞伎が来市しています。これには子息の現人間国宝中村富十郎さんも参加しておられたようです。
86年にはバンクーバー万博の後、歌舞伎舞踊、「藤娘」「連獅子」が沢村藤十郎、中村富十郎、中村橋之助のメンバーで公演。
その後、初めての世話物での大歌舞伎が中村鴈治郎一座で。90年には鬼平でおなじみの中村吉右衛門一座の大歌舞伎「鳴神」の全米ツアーがシアトルから。2005年には坂田藤十郎襲名直前の中村鴈治郎率いる近松座の公演がありました。その他にも桜祭のゲストとして長唄や日本舞踊の公演が行なわれてきています。
Q14 黒森歌舞伎や東銀座の歌舞伎以外に、どんな歌舞伎がありますか?
![]() 黒森歌舞伎や金比羅歌舞伎のように地方に伝承保存されいるものや、様式化した大歌舞伎と離れ、現役の歌舞伎役者による「スーパー歌舞伎」や「コクーン歌舞伎」といった新しい試みもなされています。
黒森歌舞伎や金比羅歌舞伎のように地方に伝承保存されいるものや、様式化した大歌舞伎と離れ、現役の歌舞伎役者による「スーパー歌舞伎」や「コクーン歌舞伎」といった新しい試みもなされています。
Q15 東銀座で歌舞伎を見たとき、会場の後ろから「はりまや」「なりこまや」というかけ声がありました。あれはなんですか?
![]() 歌舞伎独特のかけ声は「大向こう」とよばれ役者のクライマックスの演技に合わせてかけられますのでタイミングがむずかしいです。歌舞伎座などでは専門家も雇っています。よばれるのは役者の「屋号」が普通です。
歌舞伎独特のかけ声は「大向こう」とよばれ役者のクライマックスの演技に合わせてかけられますのでタイミングがむずかしいです。歌舞伎座などでは専門家も雇っています。よばれるのは役者の「屋号」が普通です。
Q16 今回中村京蔵さん、中村又之助さんがくるそうですが、お二人と中村玉緒さんは関係ありますか?
![]() 中村家は歌舞伎には多い名前ですが、芸名であり名字ではありません。同じ中村でも歌右衛門家、雁治郎家、吉右衛門家、歌六家、勘三郎家とあります。中村京蔵さんと中村又之助さんも同じ中村ですが一門が違います。
中村家は歌舞伎には多い名前ですが、芸名であり名字ではありません。同じ中村でも歌右衛門家、雁治郎家、吉右衛門家、歌六家、勘三郎家とあります。中村京蔵さんと中村又之助さんも同じ中村ですが一門が違います。
中村玉緒さんは現坂田藤十郎、三世中村鴈治郎の妹さんです。亡き御主人勝新太郎さんは長唄界名門の出でした。
Q17 歌舞伎役者が襲名したとニュースで見たりしますが、襲名って何をつぐのですか?
![]() 名門といわれる家系は代々の名人いわれた役者の名前を世襲していきます。跡継ぎの無い場合は養子縁組よることもあります。襲名のタイミングは人気や実力に加えて興行的効果も大きな要因でしょう。
名門といわれる家系は代々の名人いわれた役者の名前を世襲していきます。跡継ぎの無い場合は養子縁組よることもあります。襲名のタイミングは人気や実力に加えて興行的効果も大きな要因でしょう。
Q18 歌舞伎の屋号について教えてください。
![]() 前記の中村家のほか、尾上家、市村家、片岡家、澤村家、市川家、実川家、松本家、坂東家が主な家系です。屋号は一門の師に従いますので前述のように同じ家系でも屋号が同じとは限りません。
前記の中村家のほか、尾上家、市村家、片岡家、澤村家、市川家、実川家、松本家、坂東家が主な家系です。屋号は一門の師に従いますので前述のように同じ家系でも屋号が同じとは限りません。
Q19 歌舞伎へ入門することについて教えてください。
![]() 梨園の出身でない場合、国立歌舞伎俳優養成所などで研修を終了後、入門した一門の師により名題を許された後、その屋号を許されます。
梨園の出身でない場合、国立歌舞伎俳優養成所などで研修を終了後、入門した一門の師により名題を許された後、その屋号を許されます。
名題というのは、入門した師により一人前と認められ芸名が許されることです。襲名のように舞台で先輩から披露されます。
Q20 歌舞伎で使う着物は代々引き継いでいくものですか? どこでつくられるのですか?
![]() 松竹衣装部などで製作保管する他、各名門家でも代々相続しているものもあります。特別の出し物の為に特注される事もあります。客席からは見えない部分にも定紋を入れるなど細かい慣習があります。
松竹衣装部などで製作保管する他、各名門家でも代々相続しているものもあります。特別の出し物の為に特注される事もあります。客席からは見えない部分にも定紋を入れるなど細かい慣習があります。